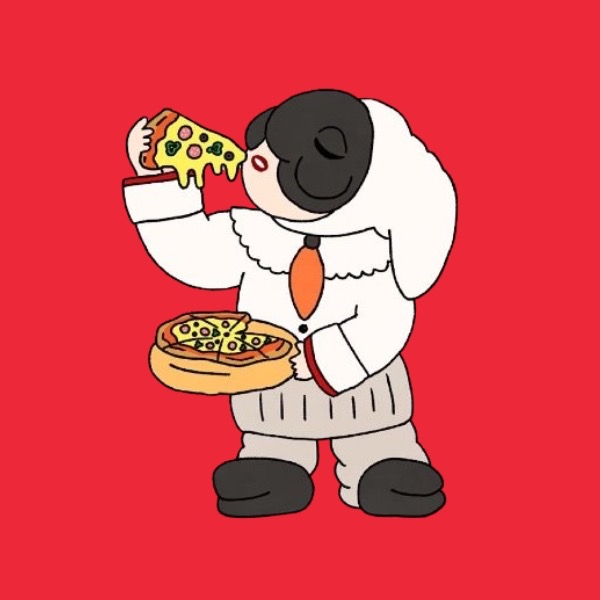カメルーン料理の謎に迫る(Nchitu’s Kitchen/清瀬)

こんにちは!オグです。
アフリカの国・カメルーン料理について、次の疑問に答えます。
- カメルーン料理って何?
- 代表的な料理を知りたい
- 地域・文化によって違いはあるのかな
- 日本人に合いやすい料理や注意点も教えて
- 食文化としてのマナー・食べ方も気になる
カメルーン料理に興味はあるけど、口に合うか不安になりますよね。イメージ湧かないですし。
- カメルーン料理の特徴
- 代表的な料理・地域と民族による違い
- 日本人が楽しみやすいポイントと注意点
- 伝統的な食べ方・食卓マナー
- 東京でカメルーン料理を楽しめる食材店「Nchitu’s Kitchen(清瀬)」
本記事の信頼性:
- 休日だけで年間365軒以上の東京にある海外グルメを開拓
- 海外グルメの専門家としてTV・ラジオ出演・記事執筆
- 70ヶ国以上に渡航し、現地の料理を開拓
- 東京で食べれる世界100ヶ国の料理をまとめたkindle本を出版しています
- カメルーン料理や食文化のイメージが湧き、未知の味を安心して体験できます
- 東京にいながら、カメルーン料理を食べれ、海外旅行しているようなワクワク感、非日常感を体験できるでしょう
ちなみに、普段はXやブログで発信していない「東京でまだ知られていない海外グルメの最新情報」をこっそりお届けする無料メルマガも用意しています。興味がある方は記事の最後でご案内しますね。
カメルーン料理ってどんなもの?
特徴

カメルーン料理は「アフリカの縮図」と称されるほど多彩で、地形・民族・歴史(アフリカ、中欧、フランス、イギリスの影響)が交錯する独特の食文化を育んできました。そのため、西洋的な調理法や食材の融合も見られます。
主食となるのはキャッサバ、プランテン(調理用バナナ)、ヤム、トウモロコシ、ミレットなどで、国土の南部では根菜とプランテン、西部ではヤムやキャッサバ、北部では穀物(ミレットなど)が主流です。これらに加えて、地理的に海に近い地域では魚介類の利用も盛んです。
代表的な料理・地域と民族による違い
代表的な料理
- Ndolé(ンドレ):ピーナッツ、現地の緑葉野菜、タマネギ、エビや牛肉などを煮込んだ国民的なシチュー。南部・ドゥアラが発祥で、フリットまたはボボロ/ミオンディ(発酵キャッサバ)とともに提供されることが多いです
- Koki(コキ):黒目豆(カウピー)とパーム油、チリをバナナの葉で包んで蒸し上げた「豆のケーキ」。西部・南西部に伝わり、プランテンと一緒に食べられることが多いです
- Ekwang(エクワン):削ったココヤムを葉に包み、魚や肉、パーム油、香辛料とともに蒸した料理。南西部の民族が発祥で、豊かな風味と食感が魅力です
- Eru(エル):エルという葉野菜とほうれん草、水菜などをパーム油、クラブ、スモーク魚や牛皮と煮込んだスープで、発酵キャッサバ粉(ウォーターフフ)と共にいただきます
- Achu(アチュ、イエロースープ):北西部地方の伝統料理。ココヤムをベースに、黄色いスープ(パーム油、石灰、スパイス、魚など)をかけて食します
地域と民族による違い
- 北部:乾燥地帯のため、穀物が中心。肉も乾燥保存などの調理法が一般的です
- 中央:ヤム、キャッサバ、トウモロコシが主食で、シチューや葉野菜との組み合わせが多いです
- 南部:キャッサバや植物性主食(プランテンなど)が主で、魚介を多用した料理も豊富です
- 植民族・儀式の食文化:バミレケ族のように儀礼料理をもつ民族もいます

西アフリカや東アフリカでは、また違った主食や味付けが楽しまれていて、とても興味深いです。
そうした「国ごとの食の違い」をもっと深く知りたい方には、ほかのアフリカ諸国のレストランも紹介しているKindle本「東京グルメで世界一周 – 世界100ヶ国の料理」が参考になります。
アマゾンの読み放題会員なら無料で、初回30日間はキャンペーンで無料体験できます。
日本人が楽しみやすいポイントと注意点
日本人が楽しみやすいポイント
発酵食品や豆料理に親しみやすさを感じる
ンドレ(緑の葉野菜とピーナッツの煮込み)や豆のスープ、発酵キャッサバなど、発酵や豆を使った料理は、日本人の味覚にも馴染みやすいです。
焼き魚に似た魚料理もあるため、魚がメインの日本人にも親しみやすいでしょう。
注意点
味付けが濃く、油やスパイスが強めです。
現地では塩やスパイス、油が多用される傾向があり、日本人には「油っこい」「辛すぎる」と感じることがあります。
伝統的な食べ方・食卓マナー
- 手洗いの習慣:食事前に濡れた布で手を拭くなど、手を清潔にする習慣が一般的です
- 共用の器と手食:共同の器から3本の指(主に右手)で主食をすくい、ソースに浸して食べます。フォーク登場は西洋化の影響で、一部地域に限られます
- 左手の扱い:食事には「右手」を使い、左手は衛生的・文化的に避けられます。導管との接触や排泄後の処理など、左手は“不浄な行為”に使う手という歴史があるためです
- 食べる順番の慣習:伝統的には年長者・男性が先に食べ、女性・子どもは後に続きます。客には特別な料理(内臓など)が提供されることもあり、拒否する際は丁寧に断る配慮が大切です
【3日前までの予約限定】カメルーン料理を出す食材店『Nchitu’s Kitchen(清瀬)』
カメルーン料理
来店3日前までの予約で作ってもらえる、カメルーンの家庭料理
予約はお店のFacebookのメッセンジャー、インスタグラムやTikTokのDMでやり取りしましょう。
今回はアフリカ料理に詳しい方が予約をしていただけました。その方によると、「アチュ」と「バンガスープ」をお願いし、フルーツカクテル付きで1人3,200円です。
実際に出てきたのが下記の料理です(4人前)
- アチュ:スープ
- アチュ:里芋で作った練り物
- 肉(ビーフ)の盛り合わせ
- バンガスープ:パームナッツの果肉を煮出して作るスープ(発祥はナイジェリア)
- ほうれん草
- フフ:タピオカの原料であるキャッサバという作物から作られます
- アフリカン・スコッチエッグ:茹で卵を魚のすり身や小麦粉の生地で包んで揚げた料理
- チンチン:丸い揚げ菓子(発祥はナイジェリア)
- プランテーンチップ(Ndjokaかな!?)
- フルーツカクテル
- 水(500mmのペットボトル1本)
総括として、かなりの量です。食べ切れず持ち帰りました(笑)。食べに行く際はお腹を空かせていきましょう!
アチュ&アチュと共に食べられる料理

真っ黄色のスープ「アチュ」は、石灰とパーム油、スパイス、魚の出汁を使って作られます。
石灰を料理に使うなんて、非常に驚きです。この石灰を加えることで、油と水が乳化し、鮮やかな黄色になるのだとか。
この料理はカメルーン北西部、特にグエンバ族やバミレケ族によって伝承され、王の料理とも称される由緒ある一品です。
王様など支配者を訪問する際に振る舞われていたことから、その名が付いたと言われています。現代でも家族の集まりや祝い事の際に振る舞わる特別な料理です。

里芋で作った練り物「アチュ」を皿に盛り、中央に凹みを作ります。そこにスープを注ぐのが伝統的なスタイルです。そして手でアチェをちぎり、スープにつけて食べます。
スープはまろやかでスパイシー、出汁の主張がはっきり現れていました。練り物は微かに甘く、ペーストのように滑らかな口溶けです。ほっとする味わいは、一度経験すると忘れられません。

里芋で作った練り物「アチュ」と混同しながちな「フフ」も今回提供されました。原料の違いはもちろん、「フフ」は「アチュ」と比べて粘り気が強いのが特徴です。
アフリカでは○○(スープやシチュー)には△△(アチュやフフ)というように組み合わせが決まっているそうです。確かにスープ「アチュ」に「フフ」を合わせてみましたが、違和感があります。
「アチュ」と「フフ」の大きな違いは下記の表を参考にしてください。
| 項目 | アチュ(Achu) | フフ*(Fufu) |
| 主な材料 | ココヤム(タロ)、場合によりプランテン | キャッサバ、ヤム、プランテン、ココヤムなど |
| 調理方法 | 茹でた後、すりつぶしてペースト状にする | 同様に茹でてすりつぶし、粘り気のある生地にする |
| 提供の形態 | 黄色いスープ(イエロースープ)と一緒に供される | 各種スープやシチューと一緒に提供される |
| 地域的な特徴 | カメルーン北西部の伝統料理 儀式的な位置付け | 西アフリカ全域で広く食される 「もち状の主食」 |
*カメルーンでは、フフは「couscous(フフ)」と呼ばれることもあり、地域によって材料や呼び名が変わります
「アチュ」と共に食べられる料理として、肉や野菜があります。

肉(ビーフ)の盛り合わせは、ボリュームが半端ないです。しかもコラーゲンたっぷり、ぷるぷるしているので、噛み切れません。顎が痛くなってしまうほどです。この中に「エグシロール」まで入っていて、非常に珍しいです。

蒸したほうれん草は、しっとりして味が滲み出ており、これまたアチュに合います。
アメリカのステーキハウスに行くと、スピナッチが付け合わせで頻繁に登場しますが、それと似た役割かなと思いました。
バンガスープ

「バンガスープ」はナイジェリア発祥で、パームナッツの果肉を煮出して作るスープです。
今回はカメルーン風になっていました。アチュに比べて、濃厚でピーナッツのようなコク、ややねっとりした舌触りが特徴です。
「バンガスープ」には粘り気の強い「フフ」が間違いなく合いますね。
アフリカン・スコッチエッグ

上記の料理以外で特に印象に残ったのが「アフリカン・スコッチエッグ」です。
茹で卵を魚(サバなど)のすり身や小麦粉の生地で包んで揚げた料理で、イギリスの植民地時代にカメルーンに伝わり、アフリカテイストとなって定着しました。

魚の旨味が前面に出た塩気のある風味です・外の衣はしっとり目、中は卵の優しい味わいでとてもおいしいです!日本のコロッケより脂っこくなく、食べやすい印象でした。
チンチン

「チンチン」はナイジェリアが発祥とされる丸い揚げ菓子です。
小麦粉、砂糖、バター、牛乳、卵など使って作られます。サクッと軽い口当たりでほんのり甘く、食べ出したら止まりません。危険な香りがします(笑)
食材店なのでテイクアウトとしてもオススメですよ。
プランテーンチップ

プランテーンチップは、完熟プランテーンを薄くスライスし、油で揚げたチップス「Ndjoka」ではないかと思われます。すみません、確認し忘れました。こちらは「チンチン」と異なり、特有の苦味としっとり感が特徴です。
「チンチン」と同様、テイクアウト可能です。


実際に私自身が訪れたレストランをまとめたKindle本では、エチオピア・セネガル・モロッコなど多彩な料理を紹介しています。
東京で楽しめるカメルーン料理をきっかけに、アフリカ各国のレストラン巡りをしてみるのもオススメです。
アマゾンの読み放題会員なら無料、初めての方は30日間無料キャンペーンで今すぐ試せます。
店舗詳細
雰囲気
- オーナーのカメルーン人の方は優しいお母さんという雰囲気で、親しみやすい方です
- 食事の前後も気さくに話しかけていただき、昔の駄菓子屋さんに似た、温かい雰囲気。ついつい長居してしまう魅力がありますね
- アフリカの未知の食材がズラリと並ぶ店内は、見ているだけでワクワクしてきます





予約・お問い合わせ
店舗基本情報
アフリカ食材店『Nchitu’s Kitchen (チトゥズキッチン)』清瀬
- 東京都清瀬市松山2-1-2
*google map上では「Nchitu & Sons合同会社」と表示される場合があります - 080-4337-7796
- 3日前までの予約限定で料理提供(食材店は予約関係なし)
- 西武池袋線「清瀬」駅 南口 徒歩5〜7分
- 08:00〜18:00(食材店)
- 日曜定休
- 現金・カード支払(できれば現金支払を希望されています)
- 公式インスタグラム
【まとめ】カメルーン料理を堪能しよう

- カメルーン料理や食文化のイメージが湧き、未知の味を安心して体験できます
- 東京にいながら、カメルーン料理を食べれ、海外旅行しているようなワクワク感、非日常感を体験できるでしょう
- ちなみに、普段はXやブログで発信していない「東京でまだ知られていない海外グルメの最新情報」をこっそりお届けする無料メルマガも用意しています。興味がある方は記事の最後でご案内しますね。
カメルーン料理の特徴:
カメルーン料理は「アフリカの縮図」と呼ばれるほど多様性に富んでおり、地形・民族・歴史的背景からアフリカ、中欧、フランス、イギリスの影響が交錯して独特の食文化を形成しています。
西洋的な調理法や食材の融合も見られるのが特徴です。主食はキャッサバ、プランテン、ヤム、トウモロコシ、ミレットなどで、地域によって根菜とプランテンが中心の地域、ヤムやキャッサバが主流の地域、穀物が中心の地域に分かれています。
また、海に近い地域では魚介類の利用も盛んで、地理的条件が食材選択に大きく影響しています。
代表的な料理・地域と民族による違い:
- Ndolé(ンドレ):ピーナッツ、現地の緑葉野菜、タマネギ、エビや牛肉などを煮込んだ国民的なシチュー。南部・ドゥアラが発祥で、フリットまたはボボロ/ミオンディ(発酵キャッサバ)とともに提供されることが多いです
- Koki(コキ):黒目豆(カウピー)とパーム油、チリをバナナの葉で包んで蒸し上げた「豆のケーキ」。西部・南西部に伝わり、プランテンと一緒に食べられることが多いです
- Ekwang(エクワン):削ったココヤムを葉に包み、魚や肉、パーム油、香辛料とともに蒸した料理。南西部の民族が発祥で、豊かな風味と食感が魅力です
- Eru(エル):エルという葉野菜とほうれん草、水菜などをパーム油、クラブ、スモーク魚や牛皮と煮込んだスープで、発酵キャッサバ粉(ウォーターフフ)と共にいただきます
- Achu(アチュ、イエロースープ):北西部地方の伝統料理。ココヤムをベースに、黄色いスープ(パーム油、石灰、スパイス、魚など)をかけて食します
- 北部:乾燥地帯のため、穀物が中心。肉も乾燥保存などの調理法が一般的です
- 中央:ヤム、キャッサバ、トウモロコシが主食で、シチューや葉野菜との組み合わせが多いです
- 南部:キャッサバや植物性主食(プランテンなど)が主で、魚介を多用した料理も豊富です
- 植民族・儀式の食文化:バミレケ族のように儀礼料理をもつ民族もいます
- 日本人が楽しみやすいポイント
カメルーン料理には日本人の味覚に馴染みやすい要素が多く含まれています。ンドレ(緑の葉野菜とピーナッツの煮込み)や豆のスープ、発酵キャッサバなど、発酵食品や豆を使った料理が豊富で、これらは日本の食文化と共通点があります。また、焼き魚に似た魚料理もあり、魚を主食とする日本人にとって親しみやすい料理となっています。 - 注意
カメルーン料理は味付けが濃厚で、油やスパイスを強めに使用するのが特徴です。現地では塩やスパイス、油が多用される傾向があるため、日本人には「油っこい」「辛すぎる」と感じられることがあります。しかし、カメルーン料理を通じてアフリカの食文化の奥深さを楽しむことができます。
- 手洗いの習慣:食事前に濡れた布で手を拭くなど、手を清潔にする習慣が一般的です
- 共用の器と手食:共同の器から3本の指(主に右手)で主食をすくい、ソースに浸して食べます。フォーク登場は西洋化の影響で、一部地域に限られます
- 食べる順番の慣習:伝統的には年長者・男性が先に食べ、女性・子どもは後に続きます。客には特別な料理(内臓など)が提供されることもあり、拒否する際は丁寧に断る配慮が大切です
- 左手の扱い:食事には「右手」を使い、左手は衛生的・文化的に避けられます。導管との接触や排泄後の処理など、左手は“不浄な行為”に使う手という歴史があるためです
【3日前までの予約限定】カメルーン料理を出す食材店『Nchitu’s Kitchen(清瀬)』

- アチュ:スープ
- アチュ:里芋で作った練り物
- 肉(ビーフ)の盛り合わせ
- バンガスープ:パームナッツの果肉を煮出して作るスープ(発祥はナイジェリア)
- ほうれん草
- フフ:タピオカの原料であるキャッサバという作物から作られます
- アフリカン・スコッチエッグ:茹で卵を魚のすり身や小麦粉の生地で包んで揚げた料理
- チンチン:丸い揚げ菓子(発祥はナイジェリア)
- プランテーンチップ(Ndjokaかな!?)
- フルーツカクテル
- 水(500mmのペットボトル1本)

- オーナーのカメルーン人の方は優しいお母さんという雰囲気で、親しみやすい方です
- 食事の前後も気さくに話しかけていただき、昔の駄菓子屋さんに似た、温かい雰囲気。ついつい長居してしまう魅力がありますね
- アフリカの未知の食材がズラリと並ぶ店内は、見ているだけでワクワクしてきます
- 東京都清瀬市松山2-1-2
*google map上では「Nchitu & Sons合同会社」と表示される場合があります - 080-4337-7796
- 3日前までの予約限定で料理提供(食材店は予約関係なし)
- 西武池袋線「清瀬」駅 南口 徒歩5〜7分
- 08:00〜18:00(食材店)
- 日曜定休
- 現金・カード支払(できれば現金支払を希望されています)
- 公式インスタグラム

- まとめて知れる → Kindle本「東京グルメで世界一周 – 世界100ヶ国の料理」
(アマゾン読み放題なら無料&初回30日間キャンペーン中)
- ほかでは手に入らない最新情報を知れる → 無料メルマガ
どちらも無料で始められるので、ぜひ気軽に試してみてください。